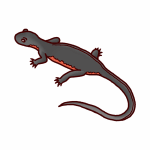 |
◆アカハライモリは、有尾目イモリ科トウヨウイモリ属に分類される両生類の一種です。
日本で単にイモリと呼ぶ場合本種を指すことが多いです。
ニホンイモリ(日本井守、日本蠑螈)という別名もあります。
全長は10cm前後で、2対4本の短い足と長い尾をもちます。
|
|
サンショウウオ類と異なり、皮膚がザラザラしています。
背中側は黒〜茶褐色で、腹は赤地に黒の斑点模様になっています。
赤みや斑点模様は地域差や個体差があり、ほとんど黒いものや全く斑点が無いもの、逆に背中まで赤いものもいます。
フグと同じテトロドトキシンという毒をもち、腹の赤黒の斑点模様は毒をもつことを、他の動物に知らせる警戒色になっていると考えられています。
陸上で強い物理刺激を受けると横に倒れて体を反らせ、赤い腹を見せる動作を行います。
イモリは脊椎動物でも、特に再生能力が高いことでも知られています。
多くの脊椎動物では、尾ですら再生することはできません。
トカゲは尾を自切し、再生することで知られていますが、実は尾骨までは再生しません。
これに対して本種は、尾を切ると完全に骨まで再生し、四肢を肩の関節より先で切断しても、指先まで完全に再生します。
目のレンズの再生については、教科書にも載るほどです。
この再生能力の高さは、生態学的研究には障害になる場合があります。
個体識別をするためのマーキングが困難なのです。
一般に、小型の両生類や爬虫類では様々なパターンで、足指を切って、マーキング・個体識別(トークリッピング)を行いますが、イモリは簡単に再生してしまいます。
尾に切れ込みを入れても、傷が浅ければすぐ再生します。
札などを縫いつけても、やはり皮膚が切れて外れやすく、傷はすぐに再生します。 |
|
スポンサードリンク
|
|