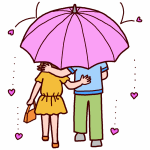 |
◆二人で一つの傘を共有する行為・態様を、相合い傘(あいあいがさ、合い合い傘、相々傘とも表記)、相傘(あいがさ)、最合い傘(もあいがさ、もやいがさ)といいます。
なにか一つのものを複数人で共用、共有すること、またその様をあらわすことばである「相合」と、「傘」を組合せ、傘を共にするさまを表しています。 |
|
連声して、東京地方や愛知県では、「あいやいがさ」とも発音されます。
また、相合傘の別称、もやいがさ(最合い傘)のもやい(催合、最合、持相、摸合、諸合)は、「共有する」、「持ち合う」を意味するハ行四段活用動詞、もやう(催合う)の連用形、名詞化したことばで、何か物事を人と一緒にとり行うことをいいます。
雨に濡れないよう互いに肩を寄せあう情景から、しばしば二人が恋愛関係であることを暗示します。
また、1920年(大正9年)に発行された『日本大辞典:言泉』(落合直文著、芳賀矢一改修、大倉書店刊)によれば、俚言、俗語として、男女間の情交もさすとしています。
男女が行う場合は、身長が女性より高いであろう男性が傘を持ち構えます。
さらには、雨にぬれるのを厭わず傘を持っていない方の肩を傘からだすことによって、二人で使うには窮屈な傘に場所をつくり女が雨にうたれてしまうのを避ける、というシーンは物語や映画などにおいてよく見られます。
前途の川柳の中には、女性側も気を使い、結果両名とも肩を濡らす情景を詠んだものもあります。
恋愛を主題にした物語においては、恋愛のステップを描く道具として、様々な状況で相合い傘は盛んに使われます。 |
|
スポンサードリンク
|
|